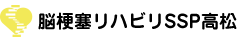脳梗塞とリハビリ方法
こんにちは!脳梗塞リハビリSSP高松 理学療法士の井上です。
現在様々な疾患に対してのリハビリ方法があります。ここ、SSP高松でも脳梗塞などの脳血管疾患を対象としたリハビリを日々行っております。今回は脳梗塞に対するリハビリ方法をいくつかご紹介していきたいと思います。
【目次】
・脳梗塞とは
・脳梗塞による後遺症
-片麻痺(運動麻痺)
-感覚障害(感覚麻痺)
-高次脳機能障害
・脳梗塞後はなぜリハビリが必要か
・脳梗塞に対するリハビリの効果
・脳梗塞後の機能低下に対する対策
・余談
・脳梗塞に対するリハビリの期間
・脳梗塞に対するリハビリ方法
-脳梗塞による運動障害
-脳梗塞による日常生活動作障害
-脳梗塞による歩行障害
-機能改善と活動維持のための脳梗塞患者および家族教育
-脳梗塞による失語症および構音障害
-脳梗塞による高次脳機能障害
・脳梗塞後の生活期でのリハビリ
・脳卒中後の保険外リハビリサービスとは
・脳梗塞リハビリSSP高松とは
・脳梗塞リハビリSSP高松の特徴
【脳梗塞とは】
脳梗塞とは脳を栄養する動脈に閉塞、または狭窄のため脳虚血をきたし、脳組織が酸素又は栄養不足のため壊死又は壊死に近い状態になることをいいます。脳梗塞の原因として高血圧や糖尿病、心疾患などを患っている方が多くみられます。現在、日本においても年間で約20~30万人の方が脳梗塞を含む脳卒中を発症しており、ほとんどの方が早期からのリハビリを取り組まれていますが、日々の生活習慣で発症の予防と対策を行う事が重要です。脳梗塞などの脳血管疾患を発症してしまうと6割以上の方が後遺症に悩まされているというデータもあります。様々な後遺症があり、病院を退院した後でもリハビリを継続する方は少なくありません。後遺症といっても様々なものがありますので次は代表的な後遺症をご紹介させていただきます。
【脳梗塞による後遺症】
脳梗塞により脳組織の壊死又は壊死に近い状態になることで脳の様々な機能が破綻してしまいます。脳には身体の様々な機能の司令塔であり中枢となっています。そこが機能障害を起こすことで手足の運動や姿勢調節、感覚、記憶や喜怒哀楽などの情動系など様々な問題が発生します。以下に代表的な後遺症をご紹介いたします。
-片麻痺(運動麻痺)
脳梗塞の後遺症で一般的によく見られる後遺症です。障害部位の対側の手足に出現する運動麻痺です。脳梗塞は中枢神経といわれる神経の損傷のため筋肉の緊張が高まりやすくなります。肩を挙げようとしても肘や指まで曲がってしまったり、足を伸ばそうとするとつま先まで伸びたりするなどの症状が見られます。
-感覚障害(感覚麻痺)
感覚障害も脳梗塞の後遺症では代表的なものになります。基本的には運動障害と同じで障害部位の反対側の手足などに症状が出現します。感覚は体性感覚といわれており、表在感覚と深部感覚に大別されます。表在感覚とは皮膚や粘膜の感覚で温度核、痛覚、触圧覚があります。深部感覚は筋肉や関節、骨などから伝えられる感覚で目を瞑っていても自分の手足がどの位置にあるのか、どの方向に動いたかなどが分かる感覚です。
-高次脳機能障害
高次脳機能障害とは言語、行為、認知、記憶、注意、判断などが障害されたことにより、失語、失行、失認、記憶障害、注意障害、半側空間無視などをきたしている状態の事を指します。頻度の高いものとしては失語症、半側空間無視、注意障害、記憶障害などがあります。また、脳血管疾患の中でも高次脳機能障害の出現率は脳梗塞発症者に多く見られているという報告もあります。
【脳梗塞後はなぜリハビリが必要か】
現在、脳梗塞などの脳血管疾患や運動器疾患など様々疾患に対するリハビリが各病院や施設などで日々行われています。脳梗塞発症後の急性期(発症から約2週間程度)からでも、早ければ発症翌日からリハビリが行われる場合があります。脳卒中治療ガイドラインにも、リスク管理を行い積極的なリハビリをできるだけ早期から行う事は推奨されているため、リハビリによる早期離床は一般的となっています。急性期リハビリの治療目的は廃用症候群の予防と日常生活動作の再獲得などがあります。脳梗塞後の機能回復は発症早期ほど良好であり時間の経過とともに緩徐になることが多いため早期から取り組むことが重要になります。また、急性期でのリハビリがその後の日常生活動作の自立度向上や入院日数の短縮化、施設入所率の低下、社会復帰率の向上、死亡率の低下に貢献するという報告もあります。これらの理由により脳梗塞後のリハビリは早期から取り組む必要があると考えられています。
【脳梗塞に対するリハビリの効果】
脳梗塞による後遺症として片麻痺(運動障害)、感覚障害(感覚麻痺)、高次脳機能障害などを挙げさせていただきました。これらはリハビリの現場ではよく見られる症状でありそれに対するリハビリの報告も多く上がってきています。運動障害へのアプローチを中心として考えた場合、様々な手技もある中で、現在は麻痺が出現した手足などに対する訓練の量や頻度、課題特異性を重視した訓練が中心とされています。近年ではロボットを使用し運動を促すリハビリも増えてきました。これらの事からとにかく不使用の時間を減少させることで機能向上を図ると考えられています。
【脳梗塞後の機能低下に対する対策】
脳梗塞以前に、人の身体は数十兆個の細胞からできており、その細胞が常に合成と分解を絶えず繰り返し行われています。筋肉で例えると、身体への刺激が大きければそれに対応できるように筋細胞が合成されることでより筋肉量が増加します。一方、筋肉への刺激が小さくなれば必要以上の筋肉は分解されることで筋肉量が減少します。脳梗塞発症後筋力低下はみられますが、長期的な筋力低下は脳梗塞による運動障害や感覚障害などから手足の不使用により起こる二次的な筋力低下ということになります。そのため麻痺が出現した手足こそとにかく使用していくことが麻痺の改善にも繋がると考えています。
【余談】
以前、脳梗塞を発症したある女性の方からお問い合わせをいただきましたので簡単にご紹介いたします。その方は脳梗塞を発症しましたが、短期間で退院が可能となり現在は自宅で生活をしております。退院後に脳梗塞の後遺症について調べていると筋肉が徐々に固くなったり、徐々に筋力が落ちたりするということを知ったそうです。対策を調べていると当事業所のHPを見つけたことでお問合せしていただきました。脳梗塞後徐々に筋肉が固くなったり、筋力が落ちてしまうことに対しては先ほどのお話をさせていただきました。あくまでも脳梗塞などの脳卒中は進行性の疾患ではないため、運動麻痺などにより筋力は落ちますが、長期的に見た場合の筋力低下などは不使用が原因の一つのためストレッチングや筋力訓練などを行うことで予防することが大切です。
【脳梗塞に対するリハビリの期間】
ここまででリハビリの重要性はご理解いただけたと思います。次はどれくらいの期間リハビリを行うかというところをお話させていただきます。その前に、先ほどもお話させていただきましたがリハビリの開始時期は早期に越したことはありません。早期よりリハビリに取り組むことで様々なメリットがあるため早期から行わない理由がないくらいです。また、脳梗塞発症から半年ほどでプラトーといわれる停滞期に入ります。入院中のように著しく機能・能力向上が見られにくくなります。しかし、「脳の可塑性」という言葉があり、最近の研究では停滞期に入ってもリハビリ次第では改善が見込めることが実証されています。麻痺の程度によりリハビリを行う期間は様々です。基本的には使わないと衰えてしまうため方法は様々ですがリハビリは半永久的に必要と考えております。簡単な内容から習慣化していくことで活動頻度を高めることが重要です。
【脳梗塞に対するリハビリ方法】
次は脳梗塞などの脳卒中を対象としたリハビリ方法でも脳卒中治療ガイドラインより推奨されたリハビリ方法をいくつかご紹介していきたいと思います。
-脳梗塞による運動障害
脳梗塞の運動障害に対してのリハビリは、課題に特化した訓練の量もしくは頻度を増やすことが推奨されています。また、自立している脳梗塞の方は集団でのサーキットトレーニングや有酸素運動を行う事もおすすめです。
-脳梗塞による日常生活動作障害
日常生活動作を向上させるために、姿勢保持能力や下肢運動機能の改善を目的とした訓練や、麻痺側上肢を強制使用させる訓練、課題志向型訓練、鏡を用いた訓練、ロボットを用いた訓練などが高い推奨度となっています。また、反復性経頭蓋磁気刺激、経頭蓋直流電気刺激、電気刺激療法を行うは妥当とされています。
-脳梗塞による歩行障害
歩行障害を改善させるために、頻回な歩行訓練は強く勧められています。また、歩行可能な発症後早期脳卒中患者に対して、歩行速度や耐久性を改善させるためにトレッドミル訓練、下垂足(つま先が上がらず垂れ下がっている状態)を呈する脳卒中患者に対して、機能的電気刺激を行う事も勧められています。また、脳梗塞や脳卒中患者でよくみられる足部の内反尖足がある患者に対して、短下肢装具の使用することも妥当とされています。
-機能改善と活動維持のための脳梗塞患者および家族教育
脳梗塞患者と家族もしくは介護者を対象とした多職種チームによる情報提供(基本動作および日常生活動作の現状、継続的な訓練の必要性とその内容、介護方法、脳梗塞などの脳卒中発症後のライフスタイル、福祉資源など)と脳梗塞を含む脳卒中知識の啓発が勧められており、患者本人だけでなく家族などの関りも重要になってきます。
-脳梗塞による失語症および構音障害
失語症に対しては系統的な評価を行い、言語聴覚訓練を行う事が勧められています。構音障害に対しては言語訓練を行う事は有効性が確立していないため弱い推奨となっていました。
-脳梗塞による高次脳機能障害
脳梗塞などの脳卒中発症後に認知機能障害の有無や程度を評価する事は勧められており、またその有無や程度の評価結果を脳梗塞患者の家族に伝えることは妥当であるとされています。半側空間無視に対しては反復性経頭蓋磁気刺激、経頭蓋直流電気刺激、視覚探索訓練、プリズム眼鏡を用いた訓練、記憶障害には記憶訓練、注意障害に対してはコンピューターを用いた訓練、代償法の指導、身体活動や余暇活動を行うことなどが妥当とされています。
【脳梗塞後の生活期でのリハビリ】
脳梗塞などの脳卒中発症から約半年間は病院に入院しながらリハビリを行う方が多くいらっしゃると思います。入院中より様々なリハビリを行うことで機能的、能力的に回復し社会復帰される方もいらっしゃいますが、そうでない方がいらっしゃるのも事実です。実際、脳梗塞発症後、後遺症に悩まされている方が約8割もいるというデータもあります。入院中は約半年間ほぼ毎日リハビリを行うことで麻痺の改善が見られますが、入院期限の上限があるため目指していた目標に到達する前に余儀なく退院を勧められた方もいらっしゃると思います。退院後の生活期では介護保険などを利用したリハビリも可能ですが、入院中のリハビリと比較すると頻度、時間ともにリハビリの総量が減少してしまいます。自主訓練もインターネットなどで探すことは可能ですがそれが自分に合った方法かどうかわからない場合も多いかと思います。そんな中で今年の三月から新しいリハビリ事業所が香川県高松市に誕生いたしました。
【脳卒中後の保険外リハビリサービスとは】
現在ほとんどのリハビリサービスは保険制度により一割負担などで賄われています。しかし、保険外リハビリサービスとは介護保険や医療保険などの公的サービスを一切使用せず利用者様の10割負担で行うリハビリサービスです。最近では「自費リハビリ」と耳にすることがあり、全国的にもそういった施設が増加しています。保険外での特徴として、日数の制限がないため利用者様の納得がいくまで利用することが可能であり、病院ではリハビリ担当が選べないが保険外リハビリでは利用者様が主体となって担当者を選べることが大きなメリットとなります。そして、私たちは 保険外リハビリ事業所「脳梗塞リハビリSSP高松」を高松市桜町にオープンいたしました!!次はSSP高松のご紹介をしたいと思います。
【脳梗塞リハビリSSP高松とは】
全国的に保険外リハビリサービスが増えている中、香川県を含め四国内ではそういったリハビリサービスはインターネット検索でほとんどヒットしませんでした。しかし、今年3月に香川県では初となる脳梗塞特化型リハビリ事業所を高松市桜町にオープンいたしました。ここでは、保険サービスでは物足りない方や年齢によって介護保険などを利用できない方、職業復帰に向けて訓練など行っているがなかなか良くならない方なども目標達成に向けて「とことん」納得・満足するまでリハビリを行う事ができます。
大阪など他県の保険外リハビリ施設に行かれたこともある方からは、「ついに高松にもできたんだね。期待しているよ」と有難いお言葉もいただきました。大阪では施設数も多く利用することが一般的になっているようです。
【脳梗塞リハビリSSP高松の特徴】
脳梗塞リハビリSSP高松の特徴といたしまして3つご紹介いたします。
-目標に合わせたオーダーメイドのリハビリと自宅課題を組み合わせたリハビリプラン
-一回120分間、完全マンツーマン制のリハビリサービス
-回復期病院でリハビリの研鑽を積んだ理学療法士が実施
これらにより保険内では難しいリハビリの量と質を確保することで短期的かつ集中的に改善を目指します。
「思っていたように身体が回復していない」
「自分で運動してきたけど成果がいまいち出ていない」
「今のリハビリだけでは物足りない」
などストレスに感じていることがありましたらご相談ください。
今通われている方も初めは不安な様子で来られましたが、良くなっていることを実感し、新しい目標へ向かって進んでいます 。
SSP高松では、日常生活でのお悩みを共有させていただくことで、それぞれに合ったプランをご提供いたします。また、施術中の動画などを撮影することで問題点などを見える化いたします。そういった情報共有を行いながら一つ一つの問題点に向き合って改善をサポートさせていただきます。
現在体験プログラムも実施しておりますので、脳卒中の後遺症でお悩みの方はお気軽にご相談、お問合せください。
住所:香川県高松市桜町2丁目15-46 チェリータウン101
電話:087-802-1290
脳梗塞リハビリSSP高松
理学療法士 井上