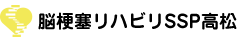脳卒中とリハビリテーション
 こんにちは、脳梗塞リハビリSSP高松 井上です。
こんにちは、脳梗塞リハビリSSP高松 井上です。
生理学が得意な私から、今回も脳卒中とリハビリテーションについてお話させていただきたいと思います。
前回はリハビリテーションの定義や内容、香川県の病院、施設紹介などさせていただきました。今回は、脳卒中の概要や種類など、また推奨されているリハビリ方法や効果などについてご紹介させていただきたいと思います。
目次
・脳卒中
-脳出血とは
-脳梗塞とは
-くも膜下出血とは
-脳卒中の危険因子
-脳卒中の予防
・リハビリテーション
・脳卒中治療ガイドラインとは
・脳卒中後の急性期リハビリテーション
・脳卒中後の亜急性期以降のリハビリテーション
-脳卒中後の回復期リハビリテーション
-脳卒中後の生活期リハビリテーション
・脳卒中後の機能、能力別リハビリテーション
-機能改善と動性維持のための患者及び家族教育
-脳卒中によるの運動障害
-脳卒中後の歩行障害
-脳卒中後の上肢機能障害
・脳卒中後の保険外リハビリサービスとは
・脳梗塞リハビリSSP高松とは
・脳梗塞リハビリSSP高松の特徴

・脳卒中
皆さんも一度は聞いたことがある言葉ですよね。脳卒中や脳血管疾患、脳梗塞に脳出血等、脳血管に関する疾患名は様々ですがここではそれぞれの言葉の意味をご説明させていただき簡単にまとめておきたいと思います。
脳卒中(脳血管疾患)には、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。いずれも高血圧が最大の原因です。
高血圧が長く続くと、動脈硬化が進行し、やがて脳の血管が詰まって脳梗塞になります。
高血圧の程度が強い場合、脳の血管が破れて脳出血になったり、また脳の血管の一部分に動脈瘤ができて破裂してくも膜下出血になります。これらの病気を脳卒中(脳血管疾患)といいます(※厚生労働省HPより一部抜粋)。
これらの事から脳梗塞や脳出血の総称を脳卒中といい、脳卒中と脳血管疾患は同じ意味でとらえてよさそうです。脳卒中の種類がいくつか出てきましたので次は一つ一つ解説していきたいと思います。
-脳出血とは
脳出血とは前述したように何かしらの原因で脳の血管が破れることです。
頭蓋骨の中に脳細胞が敷き詰められていますが、その間を通る血管が破れることで血液が脳内に溢れ出ます。
その出血により脳細胞が圧迫されたり壊死したりすることで後遺症が残ったりなど様々な症状が出現します。
-脳梗塞とは
脳梗塞も前述したように何かしらの原因で脳の血管が閉塞や狭窄により詰まることです。
それにより、灌流域(かんりゅういき)の虚血が起こり脳細胞に栄養が届かず機能低下や壊死に陥ります。
脳梗塞にも種類があり、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、ラクナ梗塞とあります。
特に心原性脳塞栓症は重度の後遺症が残る可能性が高いです。
不整脈の影響が強いため安静時や運動時にかかわらず、不整脈が出現しているかたは早めに受診をお勧めします。
-くも膜下出血とは
くも膜とは脳の外側にある膜の一つです。
脳表面の血管病変の破綻によりくも膜と脳の間に出血が生じた病態です。
出血により脳表面に血がたまりますがくも膜に覆われているため血の逃げ場がなく脳への圧迫が出現し機能障害が見られます。
-脳卒中の危険因子
脳梗塞を発生させる危険因子には、高血圧、不整脈(心房細動)、糖尿病、喫煙、肥満などがあります。
この中でも、高血圧が特に重要で、高血圧が完全に予防できれば、日本人の脳卒中は今よりも約半分に減ると考えられています。
メタボリックシンドロームも脳梗塞の危険因子の一つです。
脳出血やくも膜下出血の場合は、高血圧、喫煙、飲酒が発生に関連する要因です。
脳出血の場合は、コレステロール値の異常低値(低栄養)も発生に関与します。
私が携わった脳卒中患者様もほとんどが高血圧症を罹患されていました。
高血圧と診断されていても放っておいたことで脳卒中を発症された方も少なくありません。
高血圧症の方が拡張期血圧(下の血圧)を5~6(㎜Hg)下げれば、3~5年間の脳卒中の発症を42%軽減するといるデータもありますので、早めに相談と適切な治療は脳卒中発症予防に非常に重要です。
-脳卒中の予防
先ほどもお伝えいたしましたが、脳卒中の最大の原因は、高血圧です。
高血圧の最大の生活習慣要因は、食塩の過剰摂取といわれております。
日本人は食塩摂取の多い民族ですので、脳卒中予防のためにまず行うべきことは、減塩ということになります。
また肥満体系で血圧が高い人は減量することで血圧が下がる可能性が高いです。
たばこを吸っている人や大量飲酒も脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の全てのリスクを高くすることがわかっているため過剰摂取は注意が必要です。
一方、予防につながる食べ物としては、野菜や果物、大豆製品があります。
ウォーキングなどの軽い有酸素運動で血流をよくすることも効果的です。
そして、高血圧や糖尿病、メタボリックシンドロームを早期発見するために、年に一度は必ず健診を受けましょう。
高血圧や糖尿病、心房細動、メタボリックシンドローム、脂質の異常がある人は、保健指導や治療を受けて健康管理を続けてください。

・リハビリテーション
ここまで、脳卒中の概要や種類、予防策などお話させていただきました。
ここからは、脳卒中後のリハビリテーションについてお話させていただきたいと思います。
リハビリテーションといっても理学療法や作業療法、言語療法など種類は様々です。
今回は一般社団法人日本脳卒中学会脳卒中治療ガイドライン委員会が作成した脳卒中治療ガイドライン2021から一部の情報を抜粋し推奨度の高いリハビリテーションをご紹介したいと思います。
・脳卒中治療ガイドラインとは
リハビリテーションのご紹介の前に脳卒中治療ガイドラインとはというところをご説明させていただきます。
脳卒中治療ガイドラインは一般社団法人脳卒中学会から作成されており、医学に進歩に伴い新たな脳卒中の治療技術が導入されています。
様々な知見をもとに定期的にアップデートされているため新しい情報を得ることができます。
このガイドラインを利用しているセラピストは非常に多いと思いますし、私も良く参考にさせていただいております。
・脳卒中後の急性期リハビリテーション
では、ここからは脳卒中治療ガイドラインを参考に治療内容を一部ご紹介していきたいと思います。
はじめに、急性期リハビリテーションに関連する内容ですが、
「急性期リハビリテーションの開始時期においては、合併症を予防し,機能回復を促進するために24~48時間以内に病態に合わせたリハビリテーションの計画を立てることが勧められる」
「十分なリスク管理のもとに、早期座位・立位、装具を用いた早期歩行訓練、摂食・嚥下訓練、セルフケア訓練などを含んだ積極的なリハビリテーションを発症後できるだけ早期から行うことが勧められる」
などがあります。
驚かれる方もいるかもしれませんが、脳卒中を含めご病気や怪我により入院された場合、早ければ翌日からリハビリテーションを行う場合があります。
しかも、これらはガイドラインの中でも行うべきであると強く推奨されているため回復にはできるだけ早期から行うリハビリテーションが必要ということになります。
・脳卒中後の亜急性期以降のリハビリテーション
急性期リハビリテーションでは早期からのリハビリテーションが推奨されていますが、発症から間もないため血圧などの体調を考慮しながら行っていきます。
そのため、運動負荷量も基本動作といわれている寝返り動作や座っている姿勢をキープしたり、立つ姿勢をキープしたりなどが多い印象です。
亜急性期以降では病態も少しずつ安定してきており、発症から約半年間までは比較的回復しやすい時期となります。
ここからは、亜急性期以降のリハビリテーションをいくつかに分けてご説明していきたいと思います。
-脳卒中後の回復期リハビリテーション
回復期リハビリテーションでは、
「歩行障害が軽度の患者に対して、有酸素運動や筋力増強訓練を行うことが勧められる」
「回復期において訓練時間を長くすることは妥当である」
といった内容が推奨されています。
回復期病棟入院中の患者様で、リハビリテーション時間が長い人ほど日常生活動作レベルの向上が高くなったという研究結果も出ています。
訓練の質はもちろんですがとにかく運動する時間を増やすことも回復の近道であると捉えることもできます。
-脳卒中後の生活期リハビリテーション
次に生活期リハビリテーションでは、
「在宅で生活する生活期脳卒中患者に対して、歩行機能を改善するために、もしくは日常生活動作を向上させるために、トレッドミル訓練、歩行訓練、下肢筋力増強訓練を行うことが勧められる」
「地域におけるグループ訓練やサーキットトレーニングを行うことが勧められる」
といった内容が推奨されています。
歩行に関しては歩行訓練と下半身の筋力増強訓練が強く勧められており転倒などに十分注意しながら行う事で歩行能力の向上が認められています。
また、個別リハビリテーションだけでなくグループ訓練なども高い推奨となっていたため、地域の健康教室なども積極的に参加することは改善にもつながる可能性が高いです。
・脳卒中後の機能、能力別リハビリテーション
これまでは経過時期別での推奨リハビリテーションでしたが、ここからは機能・能力障害別のリハビリテーションのご紹介を行いたいと思います。
-機能改善と活動性維持のための患者及び家族教育
リハビリテーションにおいて患者様の頑張りはもちろん重要ですが、ご本人様だけではなくご家族様のサポートも重要となっております。
そのためガイドラインでは、
「患者と家族もしくは介護者を対象とした多職種チームによる情報提供(基本動作および日常生活動作の現状、継続的な訓練の必要性とその内容、介護方法、脳卒中発症後のライフスタイル、福祉資源など)と脳卒中知識の啓発が勧められる」
とされており、ご家族様もチーム医療の一員となっているということです。
前回のガイドラインでも推奨はされていましたが、今回は推奨度が強い推奨となっており機能改善にはご家族様のサポートも必要不可欠ということになります。
-脳卒中による運動障害
次は運動障害の項目をご紹介していきたいと思います。
「脳卒中後の運動障害に対して、課題に特化した訓練の量もしくは頻度を増やすことが勧められる」
「自立している脳卒中患者に対して、集団でのサーキットトレーニングや有酸素運動を行うよう勧められる」
が推奨されています。
課題に特化した訓練とは、うまく歩けない場合は歩く訓練を、お箸が使えない場合はお箸を使う訓練を行う事です。
特異的な動作を反復することで身体がその動作を学習してくことから推奨されています。
-脳卒中後の歩行障害
次は歩行障害に対する推奨されたリハビリテーションをご紹介していきます。
「歩行機能を改善させるために、頻回な歩行訓練を行うことが勧められる」
「歩行可能な発症後早期脳卒中患者に対して、歩行速度や耐久性を改善させるためにトレッドミル訓練を行うことが勧められる」
「亜急性期において、バイオフィードバックを含む電気機器を用いた訓練や部分免荷トレッドミル訓練を行うことは妥当である」
「脳卒中後片麻痺で膝伸展筋筋力もしくは股関節周囲筋筋力が十分でない患者に対して、歩行機能を訓練するために長下肢装具を使用することは妥当である」
などが挙げられております。
歩行障害に対しては歩行動作などによる麻痺側へ体重をかけることが重要だと感じました。
体重を上手くかけられる場合は頻回な歩行訓練、体重をかけることが少し難しい場合は、部分免荷(身体を吊り上げて足にかかる体重を減らす)による歩行訓練、麻痺側の足の筋力が十分でない場合は長下肢装具(足首、膝を固定する装具)を使用した訓練が推奨されています。
私も回復期病院に勤めていた頃は、麻痺側股関節の筋力が十分に発揮できない患者様には長下肢装具を使用しとにかく体重をかける訓練を行い歩行能力の改善に取り組んできました。
自分の意志で筋肉の収縮が発揮できない方はもちろん、発揮する筋力が低下している方でも反復し動作を行う事で動作に必要な筋力が向上し能力向上に繋がります。
-脳卒中後の上肢機能障害
次は上肢機能障害に対するリハビリテーションです。
「軽度から中等度の上肢麻痺に対しては、麻痺側上肢を強制使用させる訓練など特定の動作の反復を含む訓練を行うよう勧められる」
「ロボットを用いた上肢機能訓練を行うことは妥当である」
「視覚刺激や運動イメージの想起を用いた訓練を行うことは妥当である」
などが挙げられております。
以前のガイドラインでは軽度の上肢麻痺に対して麻痺側上肢を強制使用することが推奨されていましたが、今回のガイドラインでは軽度から中等度の上肢麻痺に対しても強制使用は推奨されていました。
また、新しく追加になった内容としてロボットを使用した機能訓練を行う事や視覚刺激や運動イメージの想起を用いた訓練も追加となっていました。
などなど、以上が脳卒中治療ガイドラインの一部ご紹介でした。
様々なリハビリ方法がありましたが、根本的には課題特異型の訓練を反復的に繰り返すなどの運動量は絶対だなということを改めて感じました。
しかし、病院から退院後、在宅でリハビリを行う場合には訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションが一般的になります。
運動量を増そうとしてもリハビリテーションでの時間は制限があります。
また、自宅での自主訓練を行う場合では自宅環境や脳卒中の後遺症により思ったようにできない場合も少なくないと思います。
しかし、近年では保険外リハビリサービスも増加傾向となっており、香川県でもついに保険外リハビリ事業所が誕生しました!
保険外リハビリと聞いてもいまいちよくわからないという方も多いと思いますので、ここからは、保険外リハビリとは何かというところを深堀していきたいと思います。
・脳卒中後の保険外リハビリサービスとは
現在ほとんどのリハビリサービスは保険制度により一割負担などで賄われています。
しかし、保険外リハビリサービスとは介護保険や医療保険などの公的サービスを一切使用せず利用者様の10割負担で行うリハビリサービスです。
最近では「自費リハビリ」と耳にすることがあり、全国的にもそういった施設が増加しています。
保険外での特徴として、日数の制限がないため利用者様の納得がいくまで利用することが可能であり、病院ではリハビリ担当が選べないが保険外リハビリでは利用者様が主体となって担当者を選べることが大きなメリットとなります。
そして、私たちは保険外リハビリ事業所「脳梗塞リハビリSSP高松」を高松市桜町にオープンいたしました!!
次はSSP高松のご紹介をしたいと思います。
・脳梗塞リハビリSSP高松とは
全国的に保険外リハビリサービスが増えている中、香川県を含め四国内ではそういったリハビリサービスはインターネット検索でほとんどヒットしませんでした。
しかし、今年3月に香川県では初となる脳梗塞特化型リハビリ事業所を高松市桜町にオープンいたしました。
ここでは、保険サービスでは物足りない方や年齢によって介護保険などを利用できない方、職業復帰に向けて訓練など行っているがなかなか良くならない方なども目標達成に向けて「とことん」納得・満足するまでリハビリを行う事ができます。
大阪など他県の保険外リハビリ施設に行かれたこともある方からは、「ついに高松にもできたんだね。期待しているよ」と有難いお言葉もいただきました。
大阪では施設数も多く利用することが一般的になっているようです。
・脳梗塞リハビリSSP高松の特徴
最後に脳梗塞リハビリSSP高松の特徴を3つご紹介いたします。
◇目標に合わせたオーダーメイドのリハビリと自宅課題を組み合わせたリハビリプラン
◇一回120分間、完全マンツーマン制のリハビリサービス
◇回復期病院でリハビリの研鑽を積んだ理学療法士が実施
これらにより保険内では難しいリハビリの量と質を確保することで短期的かつ集中的に改善を目指します。
「思っていたように身体が回復していない」
「自分で運動してきたけど成果がいまいち出ていない」
「今のリハビリだけでは物足りない」
などストレスに感じていることがありましたらご相談ください。
今通われている方も初めは不安な様子で来られましたが、良くなっていることを実感し、新しい目標へ向かって進んでいます。
SSP高松では、日常生活でのお悩みを共有させていただくことで、それぞれに合ったプランをご提供いたします。また、施術中の動画などを撮影することで問題点などを見える化いたします。そういった情報共有を行いながら一つ一つの問題点に向き合って改善をサポートさせていただきます。
現在体験プログラムも実施しておりますので、脳卒中の後遺症でお悩みの方はお気軽にご相談、お問合せください。


住所:香川県高松市桜町2丁目15-46 チェリータウン101
電話:087-802-1290
脳梗塞リハビリSSP高松
理学療法士 井上